「3~4時間抱っこしてやっと寝たのに、眠りが浅くてすぐに起きてしまう…」
そんな悩みを抱えていた娘の寝かしつけ問題。
でも、ある日出会った「ファーバーメソッド」という睡眠トレーニング法で、生後8か月の娘がたった数日で自力で眠れるようになりました。
今回はその体験談をシェアしたいと思います。
ファーバーメソッドとは?
ファーバーメソッドとは、アメリカの小児科医・リチャード・ファーバー博士が提唱した「子どもが一人で眠る力を身につける」ための睡眠トレーニング法です。
通称「泣かせる睡眠法(Cry It Out)」とも呼ばれますが、実際には「放置する」のではなく、段階的に声掛けや様子見の間隔を延ばしていく手法です。
SNSでもセルフねんねのワードを目にするので、今の子育て界では有名なんですかね…?
私は寝かしつけで悩むまでは知らないことでした…
ここからはセルフねんね一年生の私が我が家で実践したときの様子を紹介していきたいと思います!
かぴこ家での実際の睡眠トレーニングの様子
我が家では娘が0歳8ヶ月の時に実践しました。
初日は今まで聞いたことがないくらいの大声で泣き叫んでいました。
そりゃそうですよね…
なんたって今まで毎晩3〜4時間抱っこし続けてくれた母親が急にいなくなって1人で真っ暗な寝室に入れられたのですから…
正直、あまりの泣き声にトレーニングをやめようか気持ちが揺れましたが、一度やめてまた再開したら娘が混乱してより一層辛い思いをしてしまいます…
なので心を鬼にして、以下のような感じで進めました。
寝かしつけのための準備
まずは娘にこれから寝ることを理解してもらうために、寝る前の行動ルーティンを定めました。
我が家では、16:00を過ぎたら、以下の流れで行動していきます。
『入浴 → 夕食 → 遊びタイム → 絵本タイム → 歯磨き → おむつ交換 → 19:00にセットしたオルゴール音楽が流れる → スリーパーを着せる→おやすみと伝えて寝室ヘ』
あとは寝室の環境を整えました。
- エアコンで室温調整をする。
- ベッドサイドにタブレットを置いてホワイトノイズを朝までかけ続ける。
- ベビーカメラを置いて、いつでも見守れるようにする。
タブレットでかけているホワイトノイズは、テレビのザーザー音や雨音のような音になります。
エアコンくらいの音量なのに、外から聞こえるサイレンの音やリビングの物音が気にならなくなる不思議な音なので、娘のセルフねんねには欠かせません!
ベビーカメラは自力で寝るために親は寝室から出ないといけないので、安全対策として設置しました。
起きて泣いているときに危ないことをしていないか、寝ている時はきちんと呼吸しているか、スマホですぐに確認できるので、こちらもセルフねんねの必需品!
我が家で使用しているベビーカメラについては以下の記事で紹介しています。
実際のトレーニングの様子
初日からスムーズに眠れるようになるまでの経過はこんな感じでした。
1~7日目:ベビーベッドに娘を置いたら5分間ベッドの横にいてポンポンする。その後寝室を出て3分泣いたら声をかけに行く → 次は5分、次は10分…と間隔を5分ずつ延ばす。
2日目:ベビーベッドに置いた直後の行動は変えない。寝室を出てからは5分→10分→12分と声掛けの間隔を延ばす。寝落ちするまで1時間ほどかかる。
9日目:泣く時間が大幅に短くなり、寝落ちまでの時間が数分に。
30日目:寝室に入ってから声掛けが一切不要になる。
セルフねんねができるようになるまで、大体1か月かかりました。
初めて数日は娘の悲痛な泣き声に耐えるので必死でしたが、9日ほどで泣き方が一気に変わりました。
泣くというより文句を言っているような声を出していたので、「寝室へ行く=寝る」ということが理解し始めた時期だったのかもしれません。
やってみて感じたメリット・デメリット
実際にファーバーメソッドをやってみて感じたメリット、デメリットを挙げてみました。
メリット
- 入眠までの時間がぐっと短くなった
- 夜中に目を覚ましても、自力で再入眠できるようになった
- 寝る時間を固定化できたことで1日のタイムスケジュールが組みやすくなった
- 夜の自分時間ができた
デメリット
- 初日は泣き声を聞くのが辛くて、何度もやめたくなった
- 主な情報源がネットのため、自分の子供にあうやり方の調整を自己判断しなければならず不安になった
これからやってみようと思っている方へ
ファーバーメソッドは、どの家庭にも合うとは限りません。
でも、我が家には合っていたし、娘が「眠れない赤ちゃん」ではなく「眠り方を学ぶ途中の赤ちゃん」なんだと捉えると、寝かしつけに対する気持ちがラクになりました。
私がファーバーメソッドをやる上で大切にしていたことは「親がルールを守って、一貫した態度を取る」こと。
『大泣きしているしやめよう…なんとなく再開してみようかな…』
こんな感じで対応が親の気分ベースになっていると、子供はどうしたらいいか分からず不安になるばかり…
一度やると決めたら、覚悟を決める。
泣き声は辛いけれど、その先に「自分で眠れる子ども」が待っていると信じ続けました。
ただ、子どもの様子を見てデメリットやリスクの方がメリットを上回る時や体調不良時は延期するようにしていました。
…色々書いてしまいましたが…
以上が私が娘と取り組んだファーバーメソッドでのセルフねんね習得までの記録でした!
読んでくださってありがとうございました!
同じ悩みを持つ方のヒントになれば嬉しいです。
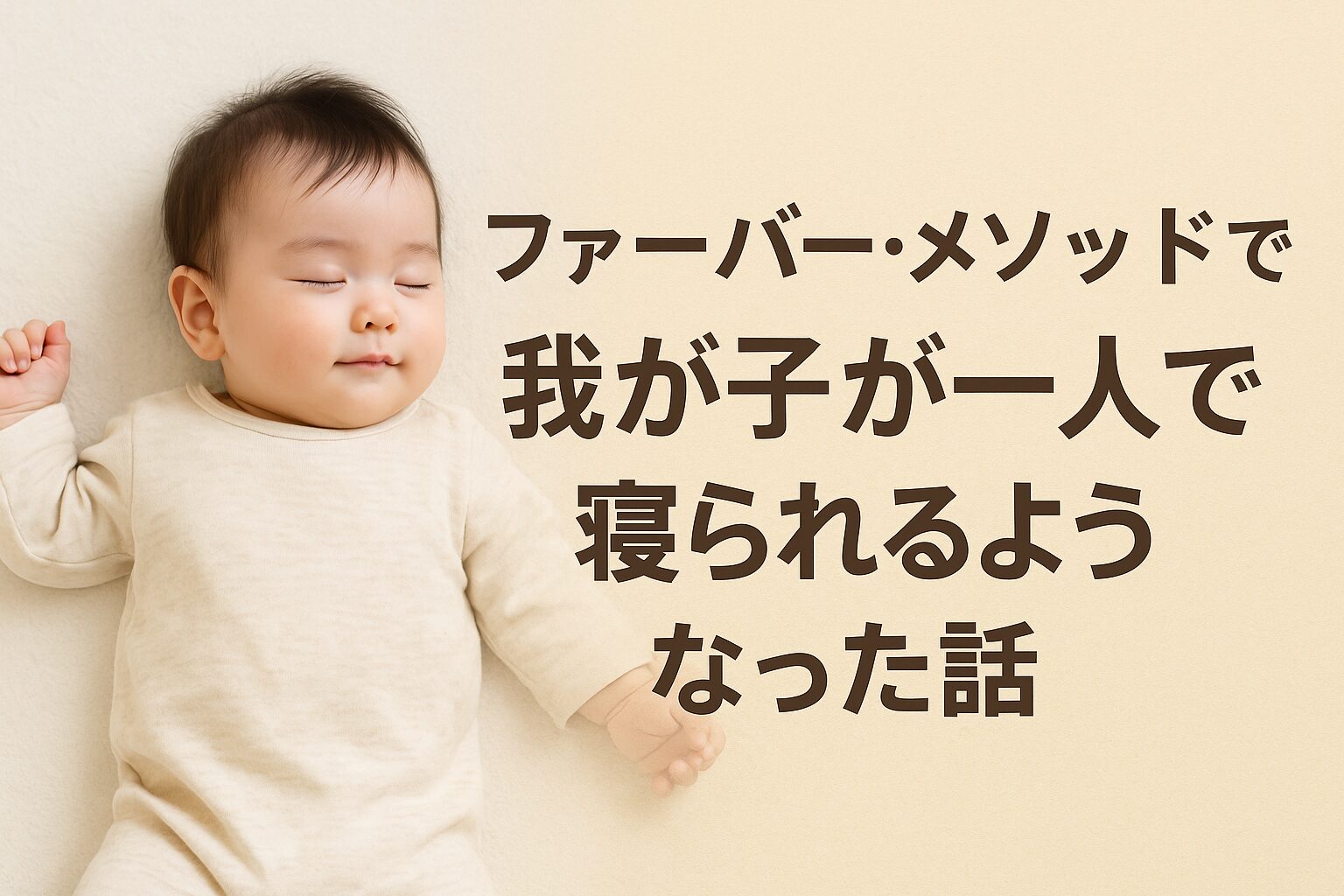

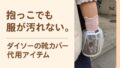

コメント